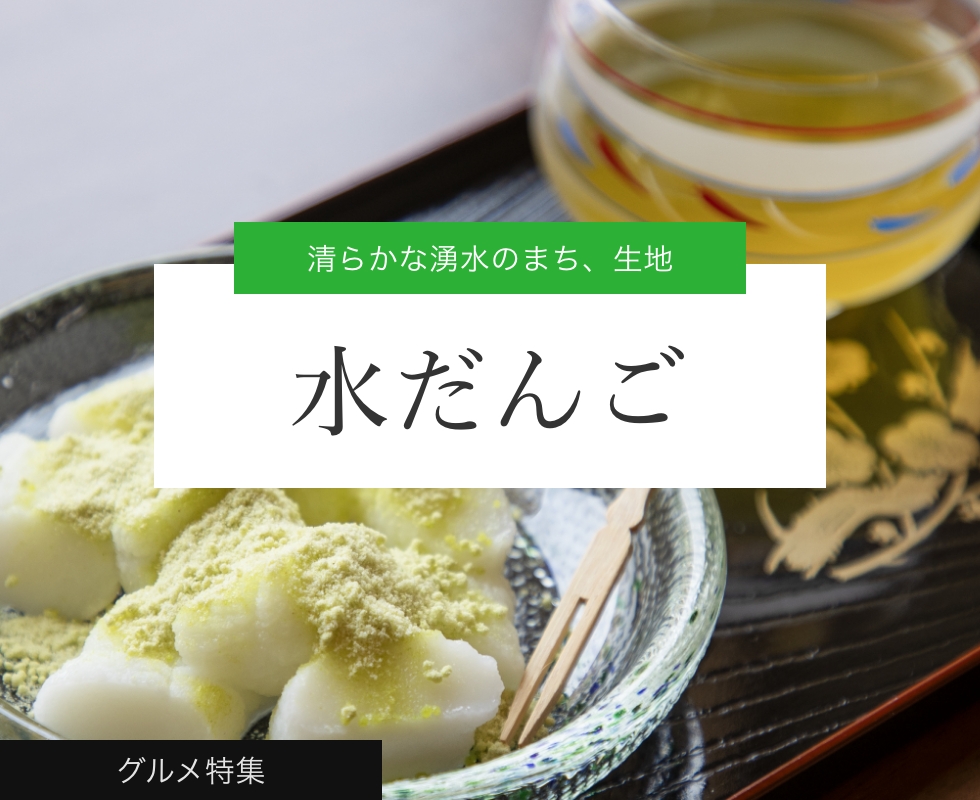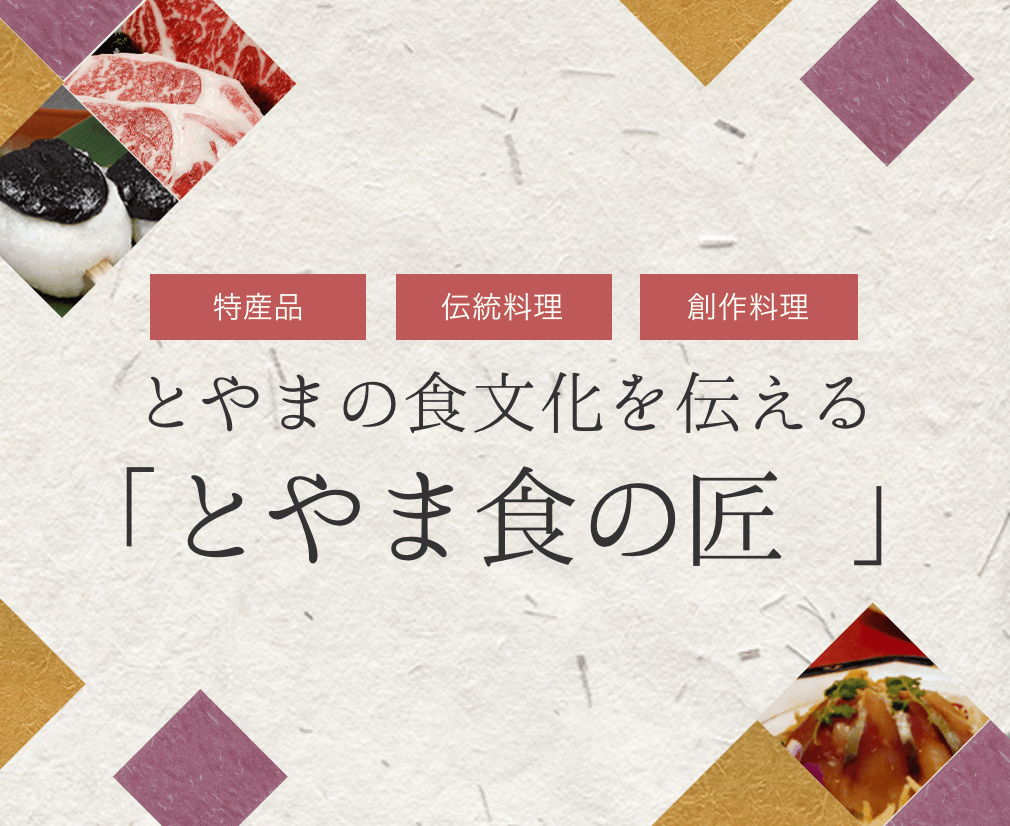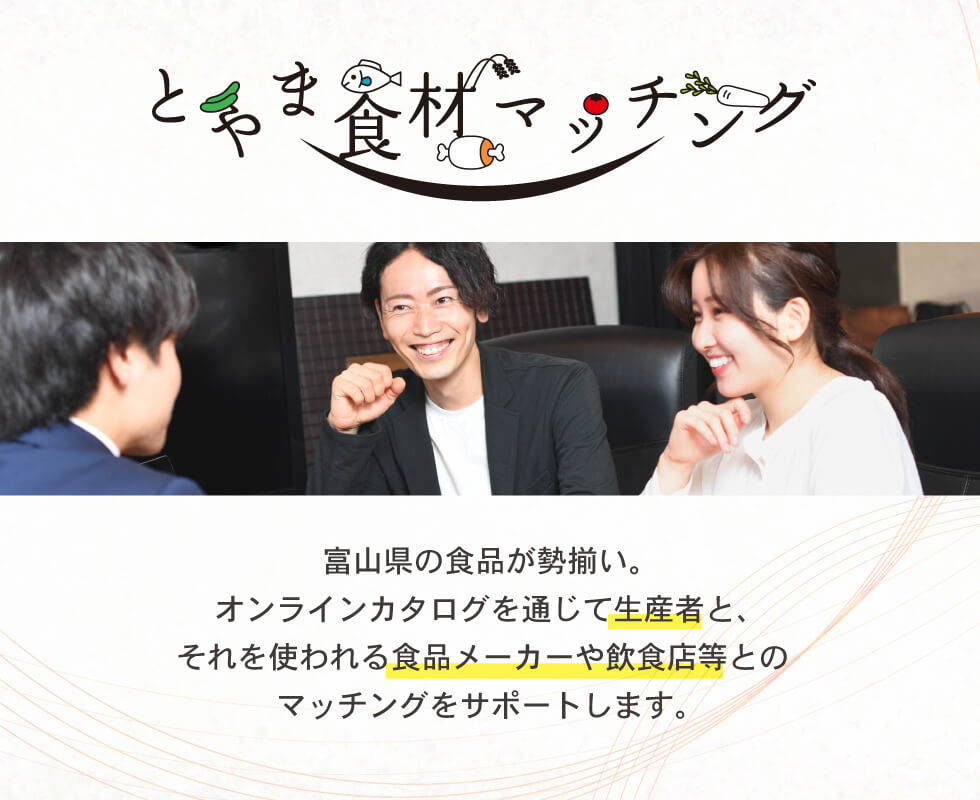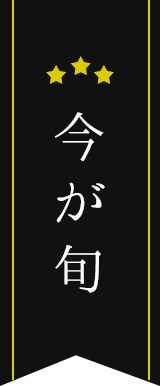ウマヅラハギ
- 旬の時期
- 12〜3月
「蜃気楼の見える街」として知られる魚津市。その観測点の魚津港では、冬になるとウマヅラハギが大量に水揚げされます。
ウマヅラハギは、頭部が長く顔が馬面に似ていることから「馬面カワハギ」と呼ばれ、全身が10~30センチの長楕円形、北海道以南の日本各地で漁獲されます。
富山湾では12月~3月にかけてよく獲れ、全漁獲量の5割程度が魚津港で水揚げされます。ピークは1~2月の厳冬期。この頃になると、体長25センチ以上ある大物が網にかかります。
ウマヅラハギは全身がぶ厚い皮で覆われており、その皮を剥ぐと中から柔らかな白身が現れます。肉質はクセがなく淡泊。食感はプリプリとして、歯ごたえがあります。肝には濃厚な旨味があり、珍味として重宝されます。近年はフグに匹敵する味わいがあるとして、市場の評価が高まっています。
こまつな
- 旬の時期
- 5〜2月
サラダや中華料理などの食材として人気のこまつな。カルシウムやビタミンなど栄養価の高い野菜としても注目されています。
富山では、甘みを増した寒締めこまつなも。出荷量は多くありませんが市場を通じて県内で販売されています。この時期だけの菜っ葉の肉厚さや甘さをご賞味ください。
ゲンゲ
- 旬の時期
- 9〜5月
日本三大深湾のひとつに数えられる富山湾には、海岸から水深1000メートル付近まで急激に落ち込む海底谷があります。300メートル以深には、水温0度に近い日本海固有水=海洋深層水があり、そこには多様な生物が存在しています。ホタルイカ、ベニズワイガニ、シロエビはよく知られた存在になりましたが、近年にわかに注目を浴びているのが、ゲンゲです。
ゲンゲは、水深200メートル以深に棲む深海魚です。体長20センチほどで細長く、身は白く透明感があります。全身がヌルヌルとした分厚いゼラチン質で覆われおり、大きなおたまじゃくしのような印象です。身は適度な脂がのっており、漁村では昔から味噌汁の具や吸い物の種として使われていました。また、天婦羅や唐揚げにすると柔らかなフワフワした食感があり、干したものを軽く炙れば酒肴として最適と評価が高まっています。
ベニズワイガニ
- 旬の時期
- 9〜5月
9月1日、ベニズワイガニ漁が解禁されると富山湾の沖合いでは、直径が1.5mある鉄製の重い「カニカゴ」が、ひとつの漁場で何百個も沈められます。水深800~1500m付近に沈められたカゴが再び引き揚げられるのは2~3日後。仕込まれた餌を求めてカゴに入ったベニズワイガニは深海から一気に漁船へ引き揚げられます。浜へ揚げられたベニズワイガニは水分が抜けないように甲羅を下にした仰向けの状態で並べられます。全身に帯びた朱色は、熱を通すとさらに鮮やかさを増し、紅葉よりもひと足早く、鮮やかな紅色で秋の到来を告げます。
冬の味覚の代表格とされるカニですが、ベニズワイガニは水温がほとんど変化しない水深400~2700mの深海で生息します。この海域の水温は0.5~1.0度程度。水深200~600mに生息するズワイガニに比べて殻が柔らかく、水分が多く含まれるのは、水圧が高い深海域に生息するためと考えられます。水分が多く、身が柔らかいことから、ズワイガニの代用品として扱われる時代が長く続きました。しかし、最近では、肉厚で身離れがよく、甲羅の味噌がとろけるように美味しいと、人気が高まっています。
富山干柿
- 旬の時期
- 11〜1月
富山県南砺市と石川県金沢市にまたがる標高939mの山「医王山(いおうぜん)」。この山のふもとに広がる南砺市福光地区では、古くから農家の冬仕事として干柿づくりが行われてきました。
歴史を遡ると、干柿の製法が慶長年間(1596~1615)に美濃の国(岐阜県)から伝えられ、江戸時代に加賀3代藩主前田利常公が、殖産施策の一環として干柿づくりを奨励したことで、今日に至る礎が築かれました。昭和40年代には、コメの減反政策を受けて、多くの水田に柿の木が植えられ、ほ場の団地化が図られました。平成30年現在は、福光と城端の両地域で約180軒の農家が従業し、年間約400万個を出荷。お歳暮やお年始などの贈答品、正月の鏡餅の飾り物として人気があります。
カンカン野菜
- 旬の時期
- 12〜2月
富山のような雪国では、昔から、秋に収穫した大根やニンジンを冬のあいだ土の中に埋めておき、雪の下で越冬保存することがあります。野菜は、寒さで凍結するのを防ごうと、凍結防止成分である糖分を増加、蓄積するといわれており、翌春に土の中から掘り起されたそれらの野菜は、収穫時より甘さを増し、サラダに、煮物にと、おいしくいただけるというわけです。「とやまカン(寒)・カン(甘)野菜プロジェクト」は平成23年からスタート。
「とやまの寒は甘い!カンカン野菜 期間限定」というキャッチコピーと、愛らしい雪だるまをマスコットに、12月下旬より県内スーパーなどで販売される予定です。