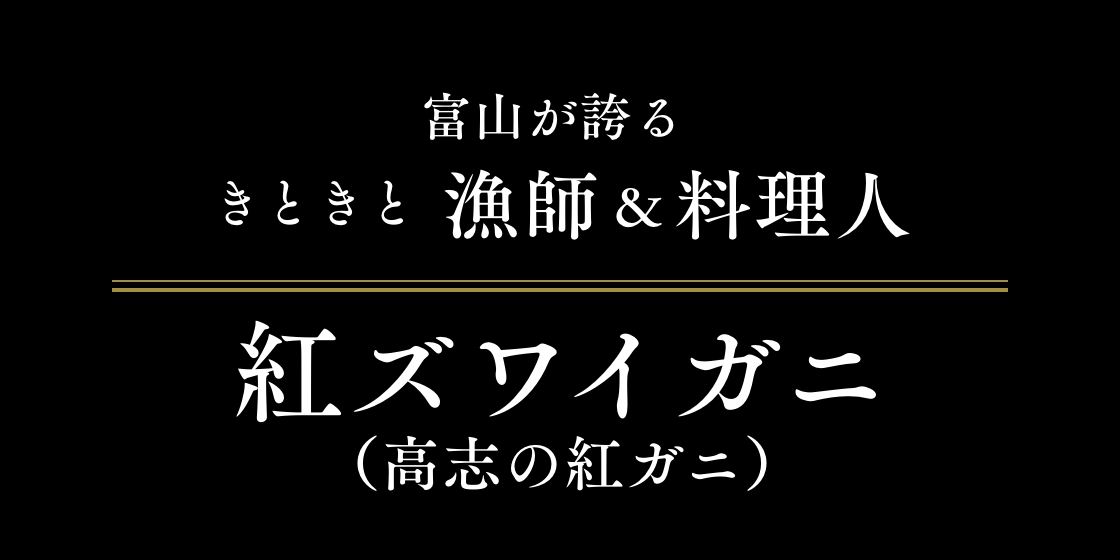漁の解禁は9月1日。水揚げされた紅ズワイガニが漁港に並ぶと、港の活気は高まり、同時に秋の到来を告げます。富山県(高志の国)の紅ズワイガニ「高志の紅ガニ」は、ズワイガニより全体に赤身が強く、雄は脚の長い点が外見上の大きな特徴となっています。身肉のジューシーな甘みと、甲羅内の味噌のとろけるような美味しさが絶妙なハーモニーとなって口の中へ。肉厚で身離れがよく、食べやすさも抜群です。何と言っても、茹でて食べるのがイチバン!お寿司や酢の物にも最適です。
甘みがスゴイ!それが、茹で上がったばかりの紅ズワイガニ
「まず、食べてみられ!取材とかは、その後や」そう言いながら第八北辰丸の親方は、茹で上がったばかりの紅ズワイガニを私たちのもとに持って来てくれた。口にしてみると…信じられないくらい甘みが凄い!美味しさがギュッと凝縮されていることを、瞬時に実感することができた。「どうや、うまいやろ!」自信満々にこちらを見て微笑む親方。その親方の傍らに、やや緊張の面持ちの若い漁師がいた。萩原力さん、28歳。親方の息子さんである。つまり親子で、紅ズワイガニ漁を行っている。

先人が開発した「エコ」な漁法「べにずわいがにかごなわ漁」
紅ズワイガニが生息しているのは、概ね水深1,000m程度の深海。ズワイガニなどと比べ、ずっと深いところにいる。こんな深海の魚介類を、底引き網や定置網などの漁法によって捕獲することは、現実的に考えにくい。漁場が深すぎて、網を置くことも引き上げることも困難だからだ。
「どうやって紅ズワイガニを獲ればいいのか…?」先人たちも、頭を悩ませていたに違いない。そんな中、富山県で開発されたとされているのが、この「べにずわいがにかごなわ漁」である。仕組みはこうだ。まずカツオなどの餌の入った籠を水深1,000m前後まで沈める。紅ズワイガニは餌を求めて上から籠の中に入るのだが、いったん入ってしまうと出るのが非常に困難な、すぼめた巾着のような構造になっている。ただし、成長しきれていない小さな紅ズワイガニまで獲るわけにはいかないから、それらは逃げられるよう、網は意図的に粗くしてある。必要に応じて自然にキャッチ&リリースできる、とても「エコ」な籠なのだ。
次に漁だが、網を深海に落とすための出航を行い、80籠程度を海に深く落とす。潮や風、雨などの気象条件などと闘いながら、絶妙の位置に落とすのが、紅ズワイガニ漁師としての腕が最も問われる部分だ。そしてその籠を、短い時は3〜4日、長ければ1〜2週間程度、海に沈めておき、今度は籠を引き上げるために海に出ることになる。
たくさんの紅ズワイガニが詰まった重い籠を、それも80籠程度引き上げるのだから「本当に大変で、強風の時などは特に苦労します。力仕事です」と萩原さんは言う。
紅ズワイガニ漁師にとって最も必要なのは「力」。そして萩原さんの名前も「力」。これは偶然だろうか…。

水揚げされた紅ズワイガニを、素早く、やさしく、茹で上げる。
水揚げされた紅ズワイガニをすぐに茹で上げるのが「滑川方式」のわけだが「深海の冷たい水で生息していた紅ズワイガニを、いきなり熱湯に入れるわけじゃないんです。体が反応して、脚なんかも身から外れてしまいがちです。だから先ずは、水とぬるま湯の中間程度のところに沈めて、紅ズワイガニたちに茹で上がるための「体の準備」をしてもらいます。それを約30分。その上で、熱湯で30分。そして最後に再度、ぬるーいお湯に戻して30分。計1時間半から2時間くらいかけての作業になります」と萩原さんは教えてくれた。もちらん単に茹でればいいわけではなく、カニの大きさや天候などによっても微妙に調節することが必要らしい。「茹でる」という行為一つ取ってみても、そこにはプロの仕事が存在している。

ズワイガニにも負けてない。
それが、自分たちの紅ズワイガニ
漁師になったきっかけなどを萩原さんに伺ってみたところ「私は次男坊ですし、本当は漁師になる気は無かったんです。兄が漁師とは違う仕事に就くとなった時、何だか“祖父や父がつないできた漁師という道を、自分たちの代で終わらせたくない”って思っちゃったんです。自分でもよく分からないんですが…」と萩原さんは自問自答するように言った。まさに、それが本音なのだろう。
そして最後に紅ズワイガニをはじめとした富山湾の魚に関し尋ねてみたところ、「富山湾の魚は、地形的な恩恵もあり、他にはないうまさがあると思う。それをしっかり広めていきたい。個人的には富山湾の紅ズワイガニは、世間一般でブランド化されているズワイガニにも負けていないと思います!」と萩原さんは胸を張った。
その時「おい、もっと偉そうな顔した写真撮ってもらえ!」と笑顔で茶化す、親方のあったかい声が聞こえてきた。

人として成長することが、料理人として成長すること。
魚津港は、岸から約10km船を走らせるだけで、1,000mの深海に達するため、カニや甘エビ、バイ貝、ゲンゲなどがよく獲れる漁場として知られている。その魚津で1908年に創業した「海風亭」では、その港から仕入れた新鮮な幸をふんだんに使用している。「紅ズワイガニは茹でた方が素材の価値を高めると思っているので、主に椀ものやカニ真薯などにして提供しています」。そう話す美浪呂哉さんは、同店の5代目料理長だ。
幼い頃から「いつかは自分も料理の道に」と、おぼろげに感じていたという。しかし「単に真似るだけでは、父を越えることができない」と感じたのか、高校卒業後から6年間ほど金沢で日本料理の修業を積み、料理の表現力や可能性を学んだ。そこで知り合ったのが、後に妻となる能登出身の佳奈さん。つまり美浪さんの料理は「魚津、金沢、能登」という複合的な視点で形成されているとも言える。
「いろんな料理を見て学んで、富山湾の魚の質の高さや、父の偉大さを再発見できましたね」と、美浪さん。人間としての幅も広げた美浪さんは家業を継ぎ、今度は魚や水など限りある資源の大切さに気づき、同業者や生産者とともに海の清掃活動なども行っている。

富山の郷土料理を、現代風にアレンジ
紅ズワイガニを使って考案した逸品は、身はもちろんのこと、殻で出汁を取るなど、素材を余すところなく使用した「紅かに真薯 呉汁(べにかにしんじょ ごじる)」。
「魚津の文化に寄り添って、魚津育ちの私しか作ることのできない料理を提供することが自身の使命だと感じています」。そんな思いから選んだのが、富山を代表する郷土料理のひとつ、呉汁だ。すり潰した大豆と根菜からなる汁物のことで、かつて味噌が貴重とされていた時代に代替のタンパク源として食されていた。だが、単に郷土料理を再現せず、和食のルーツである茶事懐石の主役・魚のすり身を使った真薯を現代風にアレンジしたところに、美浪さんのオリジナリティが光る。
実際に味わえば、紅ズワイガニやほうれん草、白身魚のすり身などをひとつに包んで蒸しあげた紅かに真薯と、温かい呉汁が見事に調和してホッとする味わい。香りづけの柚子も効いている。

富山の魚の美味しさを、世界へ発信
美浪さんの趣味は、熱帯魚のネイチャーアクアリウムづくり。「水槽の中に水草や石、流木を配置して自然と同じような生態系を作り上げるんです。そこで熱帯魚が泳ぐのを見るのが好きですね。唯一、仕事のことを忘れられる時間です」。休日さえも魚を観賞するほど魚の好きな美浪さんは、水槽に魚津の自然環境を重ねる。「山も里も海もある魚津は、世界のジオラマのよう。その素晴らしさを世界の人に知ってもらいたいです」と話す。「地方の食の今」をコンセプトに、魚津の風土、そして富山の魚の美味しさを発信する考えだ。

※こちらのメニューは、通常提供されておりません。